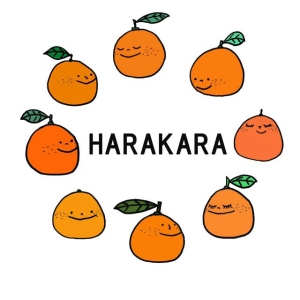いつもの風景
はらからの朝、グループホームでは夜勤の職員たちは、窓の外が明るくなるとホッとします。
「あー夜が明けた。早番さんが来る。」にわかに起きてきた利用者さんの排泄、着替え、洗面、検温、血圧測定、目薬、水分補給。それらを終えると、リビングに座っていただき、朝食を待ちます。利用者によって起床時間はまちまちです。3時、4時の方もいらっしゃれば、9時近くに起床される方もいらっしゃいます。早い日もあれば遅い日もある方がいらっしゃいます。時に、眠れない日を過ごされた方も・・・。
それぞれに朝食が終わり、与薬、歯磨き、着替は、朝食前の方もいらっしゃれば、日中活動へ行く前の方もいらっしゃいます。一連の朝の支援が落ち着くと、夜勤の職員は記録をまとめて、その内容を日中活動へスマホで送ります。早番の職員は、利用者さん一人一人のタイミングで排便支援を行います。コートを着てリュックをしょって、帽子をかぶり、日中活動の職員が迎えに来て、玄関のチャイムが、ピンポンと鳴ると、さあ一日の始まりです。朝日を浴びながら「行ってきます」「行ってらっしゃい」と言葉が飛び交います。夜勤職員と早番の職員の頭の中は、「あー今日も落ち着いてスタート出来た」とほっとします。特別のことがないいつもの風景に感謝するひと時です。
そして、いつもの風景に包まれながら令和6年度も終ろうとしていた頃に、はらからに大きなプレゼントが届きました。2月26日(大安)、「24時間テレビ」に送られた全国の皆様の義援金による福祉車両(セレナ)が寄贈されたのです。開所以来、こんなに大きな寄附をいただくというのが初めてだったので、とても嬉しくもあり、戸惑いもありました。けれど、車椅子ごと乗車できると聞き、車椅子を利用している仲間も安全に一緒に外出できるというところが気に入りました。それに新車です。
いっぱいドライブに行きたい、地域の皆様にも利用していただきたい、活動への夢が広がり思いが膨らんでいます。
御寄付をくださった全国の皆様、日本テレビ関係者の皆様、はらから一同、心から嬉しいです。感謝申し上げます。ありがとうございました。
令和7年3月20日 代表理事 槌屋久美子